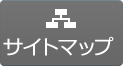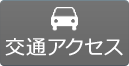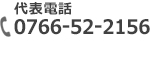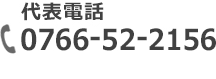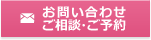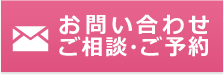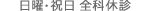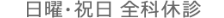親切のルーツ
先日、済生会高岡病院の地域連携懇親会に出席した時のこと。
受付で、私の顔を見るや「真鍋先生ですね。お待ちしており
ました」と笑顔で声をかけられました。済生会高岡病院の行事
に参加するのは初めてですし、その受付の女性とも初対面です。
事前に出席の連絡はしていましたので、ホームページなどで
主な参加者の顔を覚えておくように指示があったのでしょう。
それにしても、ずいぶん感動しましたし、とても爽やかな
対応に気分も晴れやかになりました。
さて、真生会はそのような対応ができているでしょうか。
事前に来客が分かっていれば、ネットなどでお相手の情報や、
可能なら、お顔を捜してみるくらいの準備をしたいものです。
もうひとつ。
同席した済生会の先生に「真生会の職員の方は皆さん、
本当に親切ですね。親戚が射水市に住んでいるので、よく
利用させていただいているそうです」と言われました。
なぜ、真生会の親切がここまで定着したのか。職員の皆さん
の努力はもちろんですが、真生会に根付いた親切の文化と
脈々と継承される親切のDNAがあるような気がします。
その親切のルーツを考えた時、ひとつは職員信条の「苦しい
時こそ和顔愛語・・・」、もうひとつは今回、装丁が刷新された
「職員心得」だろうと思いました。小学生でも分かる文章で
書かれてありますが、実行は本当に難しいと読む度に感じます。
ぜひ、この「職員心得」を身近に置いて、行間から読み取れる
精神に触れ、実行しようと努めてみてください。必ず「真生会
の職員らしい職員」になれると思います。
「私もあの人のようになりたい」と、感動を与えられる
人になれるよう、努めて行きましょう。