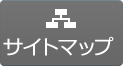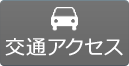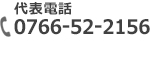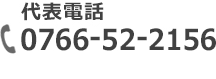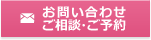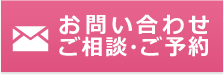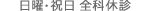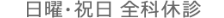利他を磨く
障害のある人にもない人にも平等の対応を行うことについて考えます。
2006年に国連で制定された障害者権利条約の基本原理は「障害者への
特別の権利ではなく、障害のない市民との平等性」です。
その基本原理に基づき、次の二つが謳われました。
1、障害を理由とした差別の禁止
2、障害者は特別な人間ではなく、特別なニーズを持つ普通の市民である
この特別なニーズへの対応のために必要なことが、ひとりひとりに適した
合理的配慮です。
「合理的配慮」という言葉がキーワードですので覚えてください。
この合理的配慮の不提供が差別にあたります。
差別というと、差別を意図して、差別的行為を「行う」ことが差別だと連想
する人が多いと思いますが、そうではなく、「何もしない」ことが差別に
なるのです。
障害者という特別の括り(くくり)を作らなくても、特別なニーズを持つ人
(何らかの事情により、特別困っている人)に対しても同じことが言えます。
特別なニーズを持つ人に何もしないことが差別になり、特別なニーズに応える
合理的配慮を行なうことが平等の対応ということです。
合理的か否かの判断は難しく、車椅子の方なら、押して差し上げると
喜ばれる方がほとんどですが、中にはそれを迷惑がられる方もあります。
ある方を特別扱いし、されなかった方が不快に思えば、それは合理的とは
言えません。
その判断が合理的かどうか。自分の配慮で、その方も周りの方も、皆が
幸せを感じるかどうか。それが判断基準だと思います。
同じ状況でも、その時その時で変わりますから、鋭敏な感覚が必要です。
利他とは、ただ与えておれば良いのではないということです。
日々、成長して行きましょう。